

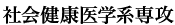

京都大学 川上浩司 2015年2月12日
2013年から2015年にかけて特筆すべき出来事としては、なんといっても民間において医療系データベースとくにリアルワールドデータ(RWD)の充実が顕著となり、これまでの医薬品のマーケティング、臨床試験、市販後安全対策といったパラダイムが大きく変わろうと胎動をはじめたことであろう。RWDが使用可能になりつつあることで、医学研究や製薬産業のあり方は本来あるべき姿、すなわちseeds drivenではなくneeds drivenへと変化しつつある。RWDをふくむ医療ビッグデータによって、臨床現場におけるクリニカルクエスチョンを解決するための臨床疫学、薬剤疫学研究がここ数年で大きく展開しつつあり、さらに、医薬品と適正な価値をきちんと訴求していくために、RWDを基盤に医薬経済学の手法によって費用対効果を追求することにも脚光が当たっている。
ITの進歩やデータベース化のノウハウの蓄積によってRWDを含む医療データの利用が可能になったことで、2014年には、注目すべき2つの報告がなされている。一つ目は国際医薬経済・治療アウトカム学会の会報誌であるISPOR Connections誌に、学会理事長の意見として、これまでのランダム化比較臨床試験(RCT)とデータベースを用いた観察研究との有用性の比較についての議論が始まったことであり、もう一つは米国内科学会雑誌(JAMA)の7月9日号において過去の薬剤のRCTの結果と、データベースを用いた観察研究の結果という異なった種類の臨床研究の主要エンドポイントを比較することで、後者でも遜色なくRCTの結果と同様の傾向を示しているという報告であった(1, 2)。これらの驚愕すべき報告は、(とくに市販後)臨床試験やマーケティング手法といったこれまで製薬企業が堅持してきた各種の経営戦略は、RWDによって既存データを活用した方向に転換せざるを得ない可能性を示唆している。
研究用途に使用可能なデータとしては、診療情報、診療報酬情報、薬局調剤情報、介護保険などのデータベースがある。これらは実際に日々の医療が行われている中で情報を整理してデータベース化したものなので、改竄、ねつ造などが不可能なRWDと呼ぶことができる。他に、国が管理しているものにもレセプト系データ(NDB)、日本外科学会で集積した手術に関する情報を中心としたレジストリ系データ(NCD)のほか、薬剤の副作用摘出と行政指導を行うためのセンチネルプロジェクトが進行しており、これにはデータ量は限定されるもののレセプトデータと医療データの両方が入っている。しかし各種データの中で、正確さでいえばレセプト系に優るものはないだろう。レセプトは、医療機関が保険者に対して医療報酬や調剤報酬を請求するためのデータであり、行われた医療行為は細大漏らさず記載されているからである。ただし、一般論としては、保険病名としての診断名や医療上のアウトカムは正確にはわからない。
医療系データを扱っている民間企業としては、まず日本医療データセンター社(JMDC)がある。同社は企業健康保険に加入する約230万人分のレセプトデータを収集している。医科入院、医科入院外、調剤、DPCとすべてのレセプトを毎月回収し、そこに記載された全項目をデータベース化しているのが特徴となっている。JMDCのデータは健保組合のさまざまな活動に活用されているのはもちろん、クリーニングした二次データが製薬企業などに提供されている。二次利用の許諾がとれているデータに関しては、我々も研究用に活用している。レセプトデータの強みは、個人の保険に紐付いているために転院しても履歴を追える点にある。ただし、レセプトはあくまでも報酬請求のための資料であり、患者の病状、検査値などは入っていない。
急性期医療におけるDPC(Diagnosis Procedure Combination)は、現在約1500病院が採用しているが、メディカル・データ・ビジョン(MDV)社が運営する、その内の約10%にあたる143施設をカバーした臨床データベースがある。DPCによる履歴がすべてデータに入っており、これを元に病院のベンチマーキングからコンサルティングを行っている企業のデータベースである。2008年4月からの年代別実患者数は総計で850万人分あり、これも二次利用データを研究用に供されている。DPCデータには治療履歴が詳細に記されているが、病院単位での記録なので、患者が転院するとその先を追うことはできない。病院内における医療行為や転帰の詳細が収載されている。
その他に、我々は、処方箋数国内トップの4社の薬局経営企業と京都大学との間で共同研究契約を締結し、調剤薬局の調剤データを、独自に設定した仮想データベースとして活用している。特定の薬剤等に注目した薬剤疫学研究を立案して、研究計画が倫理審査で承認されたのちに、当該データセットを取得、統合し、年間処方箋数にして約2000-2800万枚分のデータを解析している。これによって、日本全国で処方されている薬剤の傾向、患者、投薬量、適正使用にかかる服薬アドヒアランス、処方診療科などを検討することができる。
他には医療統計情報プラットフォーム(CISA)のデータベースも存在する。これは日本の国立大学14病院から各医療機関が保有するレセプトデータを匿名化処理した上で収集し、統合解析したものである。現在、このデータにラボでの検査データも付加する準備がされている。CISAのデータにより大学病院で行われている手術や診療の実態を掴むことができる。
ここでは、我々が実施した研究事例を4点紹介する。まず小児科領域での研究成果である(3)。この研究では、全国の高度周産期母子医療センターにあるデータの約90%を集めてきて解析した。高度周産期母子医療センターに送られてくるのは、基本的にリスクの高いケースである。こうした分娩を巡ってこれまでは、産科医と新生児科医の間で意見の相違があった。産科のガイドラインによれば、熱発や頻脈、高血圧などの症状が見られる場合は胎盤に炎症(絨毛性羊膜炎)の可能性があり母体が危険であるため、早く胎児を娩出する方が良いとされる。ところが未熟児として産まれてくる胎児を受け持つのは新生児科である。新生児科医としては、未熟児にはさまざまな発育リスクも考えられるので、母体の中で少しでも大きく育ててから娩出してもらいたい。そこで、まず各センターに残されている病理検体によって胎盤の炎症の有無をゴールドスタンダード(至適基準)として、産科の臨床的判断がどれぐらい正しかったのかを、2500の未熟児分娩例から解析した。その結果、産科医の判断の実に9割程度が正しかったことが判明した。この研究成果により、新生児科の医師のクリニカルクエスチョンの解決につながった。
次に下部消化管内視鏡(大腸ファイバー)による癌の内視鏡診断についての研究成果を紹介する(4)。下部消化管内視鏡は日本で発明されたものであり、世界的には日本ほど普及していない。したがって、日本では内視鏡診断学として確立されている学問領域の世界的なコンセンサスは未だ得られていないのが実状である。そこで、下部消化管内視鏡診断の正確さを探索するため、我々は下部消化管内視鏡の画像データと、同時に病院に蓄積されている病理の画像データを用いた診断能疫学研究を行った。これにより癌の深達度に関する判断の適切性を検証した。結果的に下部消化管内視鏡による診断の7割程度が正しかったことが確認された。日本の内視鏡診断学の有用性を世界に訴求できたことにもなる。これは、早期大腸癌の治療を内視鏡を用いて行うか、外科手術を行うかの判断に重要となる。
他には、ある製薬企業の睡眠薬開発時の治験データを使用した研究がある(5)。プラセボ効果がなぜ起こるのか、その原因に迫ったのである。本治験ではプラセボを使った二重盲検法による試験が行われた。我々はプラセボ割付群のデータを用いて、どのような睡眠の背景因子がプラセボ効果に寄与するのかを疫学解析した。これにより、プラセボ効果を起こしやすい人には、一定の傾向があることがわかった。この結果を活用して、次の睡眠薬開発時にはそうしたグループに含まれる人を治験対象者から予め除外しておけば、より少ない数の被験者で臨床試験を実施できるので、倫理的にも、開発期間の短縮とコスト削減という観点にも貢献することにつながる。
また、調剤薬局のデータ解析からも興味深い結果が浮かび上がってきている(6)。2006年から2007年にかけて新型インフルエンザが流行し、タミフルが大量に処方された。同薬を服用した子どもたちの中には異常行動に至るケースが出ており、悲惨な転落事故などを起こしている。マスコミによる大々的な報道もあったが、厚生労働省が警告した緊急安全性情報により薬の処方はどう変わったかについて、タミフル処方量の変化と、代わりに使われるようになったリレンザ処方量の変化について、調剤薬局の大規模な調剤データを用いた疫学研究を実施した。解析結果からは、厚労省当局からの注意喚起によって医師による薬剤の処方動向が明らかに変わることや、地域差が明らかとなった。こうした結果は政策的な判断に活用できるであろう。
上述の研究成果からは、医療系ビッグデータを活用することで得られるメリットとして次の3つが挙げられる。
1)医療の質が改善され、その結果が患者に還元される
2)製薬企業にとっては、市場把握、難病の同定、医薬品開発の効率化や期間短縮化などにつながる
3)医療行政や健康政策の策定において、より適切な対応が可能となる
さらに、現在世界中で取り組まれていることは、比較効用性分析(Comparative Effectiveness Research; CER)あるいは費用対効果分析(Cost Benefit Analysis; CBA)である。医療においても費用対効果の測定は重要になっている。ここにも上記の3つのポイントと同様に医療系ビッグデータを活用する価値がある。ビッグデータを用いた疫学研究に、コスト関連のデータを突き合わせることで、計量経済学の手法を用いた費用対効果研究も展開できる。現在、世界中の政府でこのような取り組みが政策として取り組まれている。日本でも平成28年度からは薬価算定時に費用対効果を勘案するプロセスの一部導入が決まっている。ただ、日本には疫学や医薬経済に携わっている研究者の少ないことが今後の懸念材料である。
データベースを用いた疫学研究と費用データを併せて使用することで、医薬品の費用対効果を厳密に測定できるようになる。例えば、高脂血症薬として使用されるスタチンは、日本とアメリカでは、そもそも心筋梗塞による死亡リスクが大きく異なっていることもあり、心筋梗塞をスタチンが一次予防する際の費用対効果は日本ではどうなのか、我々は既に報告のある欧米での例との比較もしつつ検討した(7)。
この研究では、スタチンのMEGAスタディ(Management of elevated cholesterol in the primary prevention group of adult Japanese study=高脂血症に関する一次予防大規模試験)の公開データとJALS-ECC(Japan Arteriosclerosis Longitudinal Study-Existing Cohorts Combine)の疫学データを使用した。JALS-ECCは、参加する全国の循環器疾患に関する21コホートにおいて、過去に調査された血液検査データや生活習慣の調査結果と循環器疾患発症に関する情報を一元化したものである。これらのデータを薬剤使用後の臨床経過を反映したマルコフ推移モデルに投入して解析した。例えばスタチンを投与されている場合、されていて心筋梗塞になっている場合、罹患のない場合、死亡する場合、罹患したが生き延びている場合、生き延びたが再発した場合などに細分化して、前述のデータから各分岐点における推移確率を計算した。弾き出された確率値に、次は各分岐ごとに必要な費用を挿入した。ここに仮想の患者を当てはめていき、モンテカルロシミュレーションを用いて、患者の想定条件ごとに、心筋梗塞の一次予防にスタチンを投与する費用対効果があるかどうかを判定することができる。
このような研究は海外ではもはや常識となっており、政策にも活用されている。国が新薬を承認すると自動的に薬価が決まるような国はもはや日本だけであり、世界の多数の国では、保険収載するしないを厳密に考慮しているのだ。製薬企業にとっては、このようなRWDと計量経済学の手法を用いた新たな分野をしっかり活用することで、適正な薬価の訴求や改定への対策が必要となろう。
少し毛色は異なるが、我々は、外資系の製薬企業日本法人がPMDAに新薬の承認申請を行った時のトランザクションコスト(この場合は人件費換算した交渉費用)を企業の保持するRWDの分析から実施したこともある(8)。
例えばPMDAに提出する資料を作るために、部長級1人、課長級1人、一般社員2人が一定の時間働いた場合、資料を作るのに必要となった人件費から、その制作コストを割り出すことができる。PMDAと製薬企業の日本支社の間だけでなく、同社が海外の本社とやりとりする上で必要となった費用ももれなく計算できる。こうして新薬申請プロセスをコストに焦点を絞り込んでみていくと、どの薬事プロセスで最も費用がかかっているかがわかる。すなわち業務改善の最優先ポイントが浮き彫りとなる。このケースでは臨床試験データの評価プロセスが最も大きなウェイトを占めていた。このような研究により、審査に携わるPMDAサイドも、企業サイドとしても、リソースをかけるべき部分が見えてくるだろう。
我々は、医療系以外の医療の前の部分(母子保健情報や学校健診情報)や後ろの部分(特別養護老人ホームや老人保健施設の入所時情報)といった行政資料情報のデータベース化にも取り組みはじめている。これは人間の健康史を紡ぐ「ライフコースデータ」の確立を目標としたものであり、医療の前の部分は予防医療や難病の掘り起しなど新たな産業ニーズの可視化に、医療の後ろの部分は医療の結果としてどのような人生の終末期を迎えているのかという医療の本当の意味での評価に必須であると考えている。近い将来、マイナンバー制度によって医療や健康における独立したデータベースが突合できると、既存の横断研究ではなく時間軸を越えた縦断研究として疫学研究を実施することで、例えば、子どもの頃に学校健診で特定の指摘を受けていた人が大人になった時、どのような疾患にかかりやすいかもわかる。これにより予防医療のあり方や開発すべき新薬の方向性が決まるだろう。現在、世の中には実はさまざまな情報がデータベースにならずに活用されないまま捨て置かれている可能性がある。言ってみれば宝の山がぶつ切り状態で、あちらこちらに放置されているようなものだ。ところがマイナンバー制が導入されると、各データベースにマイナンバーで横串をさして突合することで数々の知見が得られるはずである。現状では水面下に沈んでいる数々のデータを可視化することで医療の世界は大きく変わるだろう。
今後、データのデータベース化やデータベースの運用といったIT の側面に加えて、最も必要な人材は臨床疫学、薬剤疫学の研究者であり、これが今の日本の弱点である。臨床現場における素朴な疑問をひろいあげ、明らかにすべき疑問点を解消する研究デザインを組み立てていく。今の医学部あるいは薬学部、看護学部などの教育では、疫学研究をできる人材の教育に力を入れていない。ITのベンダーや情報系研究者ではなく、医療系ビッグデータを扱って新しいパラダイムの疫学研究をする研究者こそが必要である。生物統計家も危機的に不足している。ここ数年間で、新世代の疫学者の養成と基盤となる情報システムの整備が進んだ時に、医学や健康の研究や健康福祉の関わる政策のための根拠や産業は大きく変わるであろう。